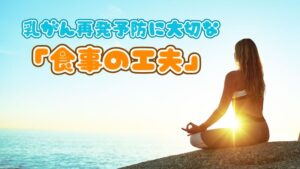9月の過ごし方、中医学で見る体調管理とおすすめの食事

9月に入っても日本の残暑は厳しく、まだまだ真夏のような暑さが続いてますよね。私が住む山梨では連日38度と、熱中症警戒アラートが毎日流れております。
しかし、暦の上では「白露」「秋分」と季節は秋へと移り変わり、体調を崩しやすい時期でもあります。
今回は中医学の観点から、9月を元気に過ごすための養生法をご紹介します。
9月は「夏の余熱」と「乾燥」に注意
中医学では、季節ごとに体調に影響を与える「気候の邪気」があると考えます。
9月はまだ夏の「暑邪(しょじゃ)」が体に残りつつ、秋特有の「燥邪(そうじゃ/乾燥)」が加わるため、以下の不調が起こりやすくなります。
9月に起こりやすい不調は?
- だるさや食欲不振
- 胃腸のトラブル
- 肌や喉の乾燥
- 気分の落ち込み
特に「脾(ひ)=消化吸収の力」が弱りやすい時期なので、暴飲暴食や冷たいものの取りすぎは控えましょう。
体はどのくらい動かすといい?

9月は涼しい日も増え、体を動かしやすくなる時期ですが、まだ暑さが残るため激しい運動よりも軽い運動がおすすめです。
9月におすすめの運動は?
- 朝晩のウォーキング
- 軽いストレッチやヨガ
- 深い呼吸を意識した太極拳
中医学では「気を巡らせる」ことが大切。無理な運動よりも、軽く汗ばむ程度が理想です。
9月におすすめの筋トレは?
筋トレが好きなのですが、8月はあまり無理しないように運動を控えていた私。
そんな私が9月行おうと思っている筋トレをご紹介します。
- スクワット(下半身強化)
→ 下半身は「脾・胃」と関わるとされ、脚を動かすことで消化機能のサポートにも。大きな筋肉を動かすので代謝アップにも効果的。 - プランク(体幹トレーニング)
→ 気を安定させる「丹田」を強化するイメージ。体の中心を整えることで、疲れにくくなる。 - ヨガ系の筋トレ(猫のポーズ・舟のポーズなど)
→ 呼吸を深めながら行うことで、自律神経のバランスを整え、残暑の疲れやイライラにも◎。 - 軽いダンベル運動(腕・肩まわり)
→ だるさを感じやすい上半身の巡りをよくし、肩こり・むくみの予防にも。
巡りをよくする、をテーマに行ってみましょう!

9月におすすめの薬膳食材
9月は「潤いを与える食材」と「脾胃を整える食材」をバランスよく取り入れるとよいでしょう。
潤いを補う食材(乾燥対策)
- 梨(喉の乾燥や咳に)
- 白きくらげ(潤いを補い美肌効果も)
- はちみつ(喉の炎症や乾燥を和らげる)
脾胃を整える食材(夏の疲れ対策)
- さつまいも(消化を助け、気を補う)
- 里芋(胃腸を温め、むくみを取る)
- 鶏肉(体力回復と気力アップ)
特におすすめは「梨と白きくらげのデザート」や「さつまいもと鶏肉の煮物」。夏の余熱を冷ましつつ、秋の乾燥に備えることができます。

9月の養生まとめ
- まだ暑いので、冷たいものを摂りすぎず胃腸を守る
- 軽い運動で汗をかき、気の巡りを良くする
- 梨や白きくらげで潤いを補い、秋の乾燥に備える
- さつまいもや鶏肉で体力を回復させる
9月は「夏から秋への橋渡し」の時期。少しずつ生活リズムを整え、秋本番に備えた体づくりを始めましょう。