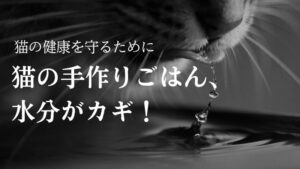【中医学と薬膳で夏を乗り切る】熱中症防ぐための過ごし方

年々厳しくなる日本の夏。熱中症はもはや命に関わるリスクのあるものとして、しっかりと予防する必要があります。
でも、ただエアコンを使って水分をとるだけでは、体のバランスは守れません。
中医学(中国伝統医学)では、夏は「心(しん)」が活発になる季節とされ、自然と調和した暮らしをすることで、心身を整えることができると考えられています。
今回は、熱中症を防ぐための過ごし方と、薬膳的な食養生についてご紹介します。
中医学でみる「夏」の体と心の変化

中医学では夏は?
夏は「陽気」が一年で最も盛んになる季節
五臓では「心(しん)」に対応し、心の働きが活発になります。
「心」は血を巡らせる働きがあり、精神の安定にも深く関係しています。
夏は暑さによって体の中の「津液(しんえき=体液)」や「気(き=エネルギー)」が消耗しやすく、心が疲れる=イライラ・不眠・動悸などの不調が現れやすくなります。
また、発汗によって水分と気を同時に失うと、熱中症のリスクも高まります。
中医学で伝えられてきた「夏の過ごし方」

「春生・夏長」=のびのびと陽気を伸ばす
春に芽吹いた生命エネルギーを、夏に思いきり伸ばす。それが「夏長(かちょう)」の考え方です。
気持ちも身体もゆったりのびやかに。ストレスをためず、笑顔で過ごすことが夏の養生の基本です。
夜は早く寝すぎず、朝は早起きを
日が長くなる夏は、早朝に起きて朝の陽気を取り込むのが理想的。反対に、夜はあまり早すぎず、涼しくなってから休むと「陰陽の調和」が保たれます。
汗をかきすぎない工夫を
汗は体内の津液と気を同時に消耗します。
・長時間の外出を避ける
・冷たい風に当たりすぎない
・吸湿・速乾素材の衣服を着る
などで、発汗をコントロールするのがポイントです。
薬膳でできる!熱中症予防の食養生

中医学の薬膳では、「清熱(せいねつ)」「生津(しょうしん)」「補気(ほき)」が夏のキーワード。
以下のような食材を取り入れましょう。
| 働き | 食材 | 効果 |
|---|---|---|
| 清熱(熱を冷ます) | 緑豆、冬瓜、きゅうり、ゴーヤ | 身体のこもった熱を排出 |
| 生津(体液を補う) | スイカ、トマト、梨、蜂蜜 | 乾燥や口渇を防ぐ |
| 補気(気を補う) | 山芋、大豆、はとむぎ、鶏むね肉 | 夏バテや疲労の予防 |
簡単!緑豆と冬瓜の養生スープ
材料(2人分)
- 緑豆 大さじ2(30分ほど水に浸ける)
- 冬瓜 100g(皮をむき角切り)
- 干しエビ 小さじ1(風味づけ)
- 水 400ml
- 塩 少々
作り方
- 鍋に水と緑豆を入れ、火にかける。
- 沸騰したら冬瓜・干しエビを加え、豆が柔らかくなるまで煮る。
- 塩で味を整えて完成。
※冷え性の方は温かいまま、暑がりの方は常温〜冷やしてお召し上がりください。
まとめ:夏は「出しすぎない」「補う」が鍵
夏は、つい冷たいものを摂りすぎたり、エアコンに頼りすぎたりと、外からの対処に偏りがちです。
でも、中医学では内側からのケア=食・過ごし方・感情の調整が重要です。
「熱中症予防=水分補給とクールダウン」だけではなく、
体質に合わせた薬膳や生活リズムで、本質的な夏バテ・熱中症予防を始めてみませんか?
季節の薬膳相談・体質チェック受付中!
中医学の知識を活かしてあなたに合った季節の養生をお伝えしています。
気になる症状がある方は、ブログのコメントまたはお問い合わせからお気軽にご相談ください。