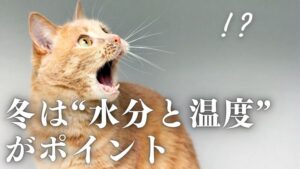薬膳×呼吸第三回!陰陽バランスを整える「片鼻呼吸 × 生姜・ミントの薬膳」
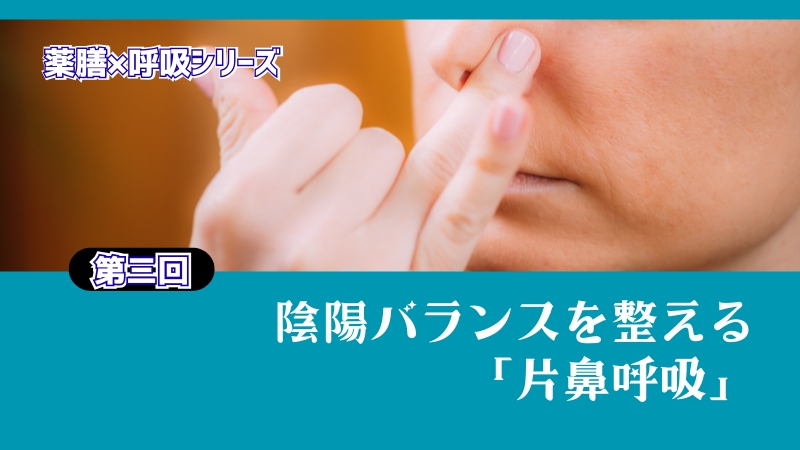
梅雨の湿気や残暑、冷房の冷えなど、日本の季節変化は“陽”“陰”的な乱れを体に与えやすい環境なんだそう。最近も急に寒くなったりして、体のバランスが崩れちゃう人、増えてきてる気がします。
そんなときこそ、呼吸法と食材を組み合わせて陰陽の調和を整えることが、体調維持・穏やかな心への近道になります。
今回ご紹介するのは、アーユルヴェーダの片鼻呼吸(ナディ・ショーダナ)と、薬膳で「温め」「冷ます」力がある生姜・ミントを組み合わせるアプローチです。
片鼻呼吸(ナディ・ショーダナ)とは?

片鼻呼吸は、古くからヨガやアーユルヴェーダで伝えられてきた呼吸法。
左右の鼻を交互に使って呼吸することで、身体の陰陽バランス、自律神経を調整するとされます。現代の研究でも、ストレス軽減や心拍数の安定に有効との報告もあります。
「ナーディ・ショーダナ(Nadi Shodhana)」はどういう意味?
- Nadi(ナーディ)=「エネルギーの通り道(気の流れ)」
- Shodhana(ショーダナ)=「浄化」
という意味です。
つまり、「ナーディ・ショーダナ」=気の通り道を浄化する呼吸法。
英語では「Alternate Nostril Breathing(片鼻交互呼吸)」とも呼ばれています。
ヨガでは、右鼻=陽(太陽・活力)、左鼻=陰(月・静けさ)とされ、
交互に呼吸することで、陰陽のバランスを整え、自律神経を調整する効果があると伝えられています。
やり方(初心者向けバージョン)
- 右手を使い、親指で右の鼻孔をふさぐ。
- 左の鼻孔からゆっくり4秒かけて吸う。
- 吸った後、軽く2秒息を止める(無理なら省く)。
- 薬指で左の鼻孔をふさぎ、右の鼻孔から6秒かけて吐く。
- 同じ手順で反対側(左から吸って右へ吐く)を行う。これを3〜5サイクル。
左右で「吸う・吐く」を交互に行うことで、左右の“気の流れ”を均衡化し、心身の調和を促すと考えられます。
鼻呼吸は実は時間によって右か左しか作用していない

人間の鼻は、数時間ごとに片方ずつ通りやすさが入れ替わる仕組みを持っています。
これを 「鼻周期(nasal cycle)」 といいます。
- 鼻の中の「下鼻甲介(かびこうかい)」という部分が、交互に充血したり収縮したりすることで、
片方の鼻が通りやすくなったり、もう片方が少し詰まり気味になったりします。 - この周期はだいたい 2〜6時間ごとに自動で切り替わるとされていて、
健康な人でも無意識のうちに常に起こっています。
なぜそんな仕組みがあるの?
実はこの鼻周期、呼吸器の「休息とメンテナンス」のために存在していると考えられています。
- 片方ずつ休ませる
片方の鼻腔が少し詰まり気味になることで、粘膜を休ませたり、乾燥を防いだりできます。 - 温度・湿度の調整
空気を温めたり、湿度を保ったりする機能を交互に分担しているため、
肺に最適な状態で空気を届けることができます。 - 自律神経との関係
右鼻の通りがよい時は「交感神経」が優位(活動モード)、
左鼻の通りがよい時は「副交感神経」が優位(リラックスモード)になりやすいとされています。
これはヨガやアーユルヴェーダの「陽(右)」「陰(左)」の考え方とも一致します。
生姜とミント:薬膳での役割と組み合わせの意義

生姜(しょうが) — 温性食材で陽を補う
生姜は中医学・薬膳で温性とされ、体を温め、血行を促し、消化を助け、寒さからくる不調を軽減するとされます。
医療研究でも抗炎症作用や代謝促進効果が確認されています。
薬膳では、寒気・冷え・疲労感を感じるときに「陽を補う食材」として使われます。
ミント(薄荷) — 涼性・清熱食材で陰を補う
ミントは「涼性(陰性)」食材として、体表の熱を冷ます、頭やのどの火照りを鎮める役目があります。香り成分(メントールなど)が神経を落ち着け、消化にも役立つという報告もあります。
薬膳では、のぼせ、汗、胸のむかつきなど“過剰な熱”に対して「冷ます力」を持つ食材として使われます。
相性が良いことの根拠は?
生姜=温め/ミント=冷ます、という対立する性質を持つ食材を適切に組み合わせることで、陰陽バランスを調える効果が期待できます。
特に片鼻呼吸で左右の調和を図った後、この組み合わせを使えば、呼吸から体への刺激をさらに整える助けとなります。
実践レシピ:生姜ミントティー
材料(1〜2杯分)
- 生姜スライス 1片(約5g)
- ミントの葉 5〜8枚(新鮮または乾燥)
- 熱湯 250ml
- Optional:はちみつ 少量
作り方
- 生姜をやや薄切りにし、カップまたはポットに入れる。
- 熱湯を注ぎ、2〜3分蒸らす。
- ミントの葉を加え、1分ほど静かに香りを移す。
- 飲みやすければ軽くはちみつで甘みを調整。
ポイント
- 初めはミントをほんの少しにして、香りの強さを調整。
- GERD(逆流性食道炎)がある方はミント量を控えるなど注意。
- 生姜は温かい性質なので、体調や季節、その日の体温に合わせて量を調整するのが◎。
この組み合わせを生活に取り入れるコツ

- 夜寝る前やリラックスタイムに呼吸法+ティーをセットに
片鼻呼吸を終えたあと、ゆったり生姜ミントティーを飲む流れにすると心身が落ち着きやすくなります。 - 香りで意識を引き戻す
ミントの爽やかな香りは呼吸を整えるときに集中力を支えるトリガーになります。 - 体調に応じて分量を調整
冷えを強く感じる日は生姜を多めに、のぼせや頭痛が強い日はミントを強めに、など調整することで自分の体と対話できます。
注意すべきこと・リスク
- GERD・胸焼け持ちの方はミントを強くすると逆効果になる場合あり。
- 抗凝固薬を服用中・出血しやすい体質の方は生姜の高用量に注意(薬理相互作用の報告あり)。
- 精油(ミントオイル等)を使う場合は希釈が必須。内服には注意が必要です。
まとめ
- 片鼻呼吸 は陰陽の流れを整える強力なツール
- 生姜 × ミント の薬膳は温・冷の性質をうまく組み合わせ、体と心をバランスよくケア
- 飲み物や呼吸法をセットに取り入れると、日常に落とし込みやすくなる
呼吸も食も、小さな選択の積み重ね。
焦らず、体の声を聴きながら、この組み合わせを暮らしに取り入れていきましょう。