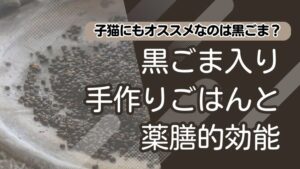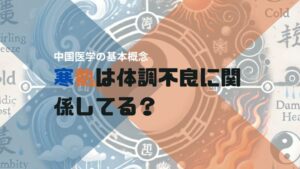中国医学の基本概念~六淫(りくいん)とは?【Q &Aで詳しく解説】

中国医学は「人は自然の一部である」という思想を根本に持っています。自然界の変化が人の体に大きな影響を及ぼすと考えます。
気候の変化が体調に影響するのは現代人にも実感しやすい現象ですが、中国医学ではこれを体系的に整理し、「外因(がいいん)」の一つとして位置づけています。
外因の代表的なものが「六淫(りくいん)」と呼ばれています。これは外部から体に侵入する病因であり、本来は自然界に存在する正常な「六気(ろっき)」が、過剰になったり人の体が弱ったりしたときに、病邪(びょうじゃ)へと転じるものです。
Q.中国医学の基本概念、六淫ってそもそも何?
A.六淫とは6つの病邪の総称なんです。
六淫とは
- 風邪(ふうじゃ)
- 寒邪(かんじゃ)
- 暑邪(しょじゃ)
- 湿邪(しつじゃ)
- 燥邪(そうじゃ)
- 火邪(かじゃ)/熱邪(ねつじゃ)
実はすべて自然界の気候と関連しているんです。
たとえば「風」は春、「寒」は冬、「暑」は夏というように、季節ごとの特徴的な気象と対応しています。
ただし、現代ではエアコンや生活環境の変化により、季節とは無関係にこれらの邪が身体に入り込むケースも珍しくありません。

Q.六淫の特徴と症状について詳しく知りたい!
A.① 風邪(ふうじゃ)
- 特徴:動きが速く、変化しやすい。風は他の邪を伴って侵入しやすい。
- 症状:悪寒・発熱、頭痛、めまい、首や肩のこり、関節の痛みなど。風寒や風熱として他の邪と組み合わさることが多い。
A.② 寒邪(かんじゃ)
- 特徴:収縮性・停滞性。陽気を損ない、気血の流れを妨げる。
- 症状:手足の冷え、腹痛、下痢、関節のこわばり、舌が白く湿るなど。
A.③ 暑邪(しょじゃ)
- 特徴:高温・上昇性・消耗性。夏に多く、体液や気を消耗する。
- 症状:高熱、口渇、多汗、倦怠感、熱中症のような状態。しばしば湿邪と組み合わさる(暑湿)。
A.④ 湿邪(しつじゃ)
- 特徴:重濁性・粘着性・停滞性。身体にこもりやすく、長引く。
- 症状:むくみ、重だるさ、胃もたれ、下痢、関節痛、舌がべたつくなど。
A.⑤ 燥邪(そうじゃ)
- 特徴:乾燥性。体液や肺の陰を傷つける。
- 症状:皮膚の乾燥、咳、喉の渇き、便秘、唇のひび割れなど。
A.⑥ 火邪/熱邪(かじゃ/ねつじゃ)
- 特徴:炎上性・消耗性。陰液を傷つけ、熱毒を生じる。
- 症状:発熱、口内炎、のぼせ、イライラ、便秘、舌が赤く苔が黄いろいなど。

Q.六淫はどうやって体に入ってくるの?
中国医学では「衛気(えき)」と呼ばれる防御のエネルギーが体表を守っているんです。この「衛気」がしっかりしていれば外邪の侵入を防げると言われています。
ですが、過労・睡眠不足・不摂生・加齢などで衛気が弱ると、六淫が体内に侵入し、風邪や胃腸障害、関節痛など多様な不調を引き起こします。
特に「風邪」は他の邪の先鋒として侵入しやすいため、「百病の長(ひゃくびょうのちょう)」と呼ばれ、非常に警戒されます。
Q.六淫と体質・生活習慣の関係について教えて!
A.六淫は単なる“外から来るもの”ではなく、個々人の体質や生活習慣によって受けやすさが異なるということです。
六淫と体質・生活習慣の関係
- 冷え性の人は寒邪に侵されやすく、
- 胃腸が弱い人は湿邪の影響を受けやすく、
- ストレスが多い人は火邪(熱邪)を内にため込みやすい。
つまり、六淫は外的なものだけでなく、内因(体の虚弱・陰陽バランスの乱れ)と組み合わさって発病することが多いのです。
まとめ:六淫を知ることは、季節と調和して生きること
六淫という概念は、単なる病名の羅列ではなく、自然と人間の関係性をとらえる漢方の知恵そのものです。季節や気候の変化に応じて自分の体を調整し、未然に病を防ぐことは、漢方における「未病治(みびょうち)」の実践です。
自分の体質と生活習慣を見直し、「今の季節、私はどの邪を受けやすいのか?」を意識するだけでも、日々の体調管理に役立つ!
一緒にゆるっと養生していきましょう!